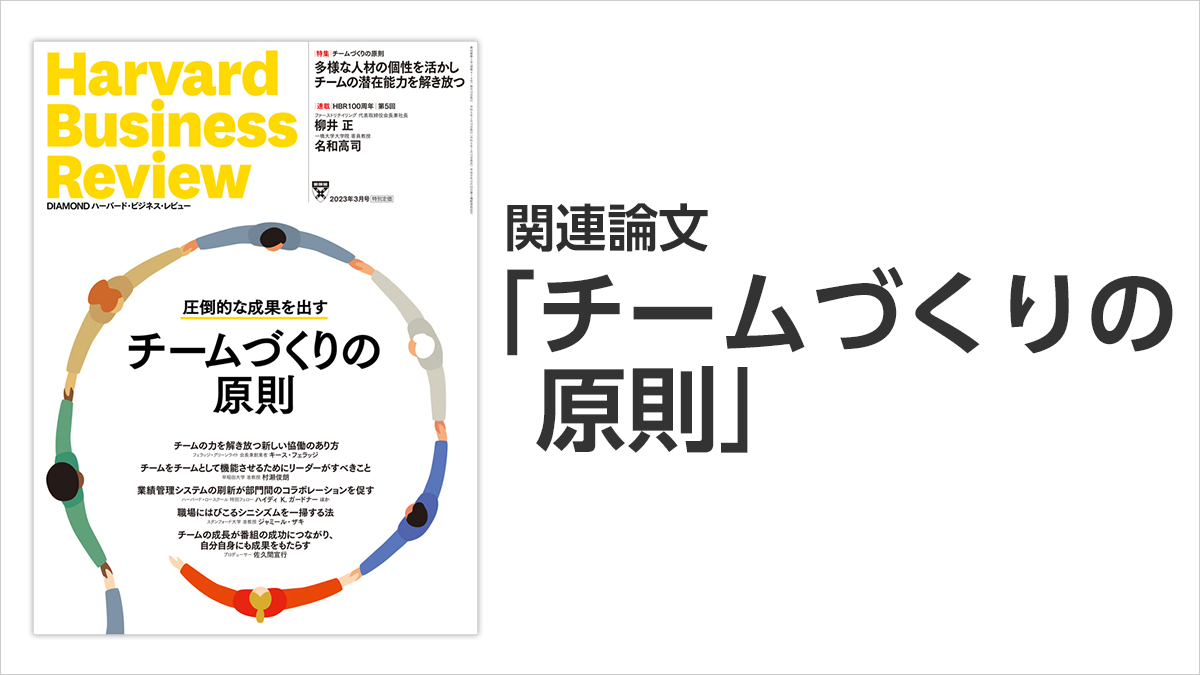
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
DHBR2023年3月号の特集は「チームづくりの原則」。不確実性の高い外部環境に適応しながら成果を上げ、飛躍的な成長を遂げようとするならば、リーダーのトップダウンや一部の優秀な専門家に頼るだけでは限界がある。チームの多様なメンバーの潜在能力を引き出し、コラボレーションを促し、イノベーションにつなげていくにはどうすればよいのか。
組織変革には、強力なリーダーシップが必要だと考えている企業が少なくない。しかし、変革は、偉大なリーダーの力に頼るのではなく、チームの変革から始めることが重要である。迅速に意思決定を行い、イノベーションを加速させるため、チームはどうあるべきか。
フェラッジ・グリーンライト会長兼創業者のキース・フェラッジは、メンバー同士で率直に意見交換し、全員が全社的な利益にコミットするという「新しい社会契約」の重要性を説く。
「チームの力を解き放つ新しい協働のあり方」では、まず優れたチームに生まれ変わるために、現在の状態を評価する簡単な診断法を紹介する。そのうえで、メンバーが率直に意見を述べ、前向きに事業に取り組む組織へと変革する、効果的な手法を解説する。
先行きが不透明な状況に適応しながら、新しいことを素早く、そしてやり続けるためには、個人の力では限界がある。そこで必要となるのがチームの力だ。チームとして連携することで、目まぐるしく変わる状況に適応し、個人では達成できないような成果を上げられる。
このチームの重要性はかつてないほど高まっている。しかし、実際にチームをうまく機能させるのは一筋縄ではいかない。
早稲田大学准教授の村瀬俊朗氏による「チームをチームとして機能させるためにリーダーがすべきこと」では、日米で10年以上チームワークを研究してきた筆者が、チームとは何か、そしてチームが機能するとはどのようなことかを論じる。そのうえで、チーム内やチーム間での連携を深め、成果につなげる方法を提示する。
コラボレーションなき縦割り型の対応は顧客の信頼を損ね、売上げを下げるばかりか、従業員エンゲージメントにも悪影響を与える。しかし、部門をまたいだ共通の成果を上げさせる際に大きな障害となるのが、個人の成果や短期目標に力点を置いた従来型の業績管理システムである。
ハーバード・ロースクール特別フェローのハイディ K. ガードナーらは「業績管理システムの刷新が部門間のコラボレーションを促す」の中で、戦略目標の達成に向けたコラボレーションを促しつつ、個人目標の達成にも責任を負わせるには、4つの視点に基づくパフォーマンススコアカードを取り入れるとよいと主張する。
他人は利己的で、強欲で不誠実だと思い込む「シニシズム」が職場で広がりを見せている。シニシズムの蔓延は、従業員のモチベーション低下やイノベーションの阻害などを引き起こす。マイクロソフトもこの問題に直面した。同社が2014年に苦境に陥った背景には、シニシズムが従業員間の不信感や競争意識、派閥意識を招いたことがある。
スタンフォード大学准教授のジャミール・ザキによる「職場にはびこるシニシズムを一掃する法」では、何十年にもわたり積み重ねられてきた研究を通じて、シニシズムの問題を明らかにしたうえで、人々がどのようにして「シニシズムの罠」に陥るか、組織のいかなる方針や慣行がシニシズムを招く可能性があるか、そして、従業員がこの罠に陥るのを防ぐためにリーダーは何ができるかについて洞察を提示する。
マネジャーがこなすべきタスクは膨大であり、チームメンバーと個別に対話の機会を持つために、時間を確保するのは簡単ではない。しかし、1on1ミーティングに時間を割かなければ、部下の成長が遅れるだけでなく、自身の成功もおぼつかない。
ノースカロライナ大学シャーロット校チャンセラーズ・プロフェッサーによる「1on1ミーティングの効果を最大化する方法」では、その効果を最大化するために、事前にいかなる準備をすべきか、そして実際のミーティングをどのように進行すべきか、具体的に論じる。
佐久間宣行氏はテレビ東京在籍時、『ゴッドタン』や『あちこちオードリー』など数々のヒット番組を手がけてきた。2021年に独立すると活躍の場を広げ、ネットフリックスの『トークサバイバー!』や自身のユーチューブチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』をはじめ、圧倒的な成果を上げ続けている。
「チームの成長が番組の成功につながり、自分自身にも成果をもたらす」では、専門性の異なる多様なスタッフ、そして個性あふれる多彩な出演者が協働で一つの番組をつくり上げるために、佐久間氏はチームをどのようにリードしているのか聞いた。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









