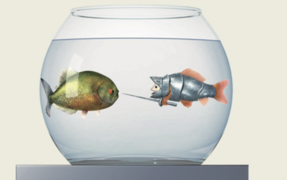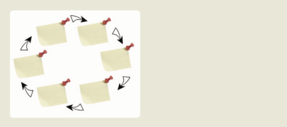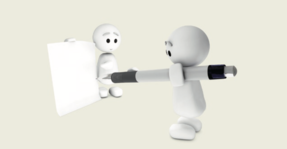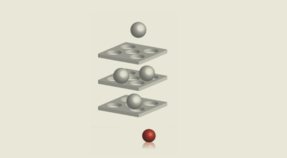-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
既存チャネルのジレンマ
従来のチャネル戦略は市場セグメンテーションを基本としている。たとえば、30代の郊外に住む女性をターゲットにしたブランドを投入する場合、ある一定のチャネルを利用して、自社商品やそれに関連するサービスを提供したり、販売活動を展開したりする。また、退職した富裕層にアプローチするならば、別のチャネルを選択するだろう。
一般的な傾向として、人口統計上、同じ特性に属する人々は、限定された同じチャネルを通じて、同じ方法でショッピングや購入を行うというのが一致した見方である。
これはごく最近までは正しい仮定だった。実際、顧客たちは必ず自分たちの領域にとどまっていた。「揺りかごから墓場まで」とは言わないまでも、せめて初期の検討段階から2度目の購入に至るまでは、特定のチャネルを利用し続けた。
そうした仮定に基づいて、たとえばメリルリンチをはじめとする証券会社は、オンライン取引を導入した当初、人口統計に基づいたセグメンテーションを利用して、ITに習熟した若年層と高齢の富裕層とで販売チャネルを分けた。後者の取引コストは取引1件ごとにかかり、割高だったが、調査リポートやアドバイスといったサービスを無料で利用することができた。
しかし、ここに問題が潜んでいた。その後高齢の富裕層はオンライン取引のやり方を身につけていったのだ。やがて彼らに向けたフル・サービスの口座は利用も投資額も減少し、このサービスの利益率も低下してしまった。フル・サービスの利用客は、証券会社が提供するアドバイスや調査リポートだけを利用して、実際の取引は格安のオンライン証券会社を利用していたのである。
証券会社の例からもわかるとおり、「特定のセグメントに商品やサービスを提供するために別のチャネルを用意する」という戦略は、もはや賢明な、あるいは今後も有効な選択肢ではない。顧客は以下のような理由から、これまで彼らが慣れ親しんだチャネルから離れてしまった。