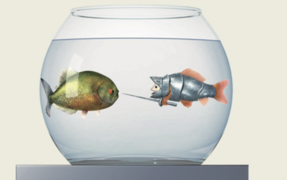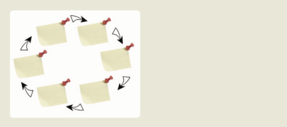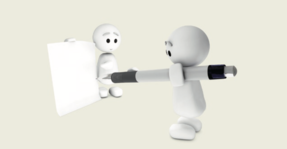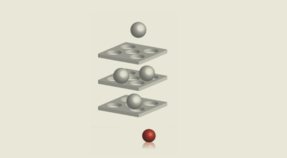-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
インタースティシャルから「ビビスティシャル」へ
消費財マーケティングに詳しい方ならば、「インタースティシャル広告」という言葉をご存じだろう。インタースティシャル広告とは、「すき間」、番組と番組の合間に登場する広告のことである。まるで高速道路の料金所のように、目的地に着く前に無理やり停止させ、視聴者に「時間」と「注意」という支払いを強要する。
30秒のスポット広告に代表されるように、このコンセプトは過去に生み出されたものであり、今日の消費者が広告を拒絶したり、飛ばしたり、ザッピング(チャンネルを頻繁に切り替えながら視聴する行為)したり、早送りしてしまう原因でもある。
広告業界の衰退はいまや周知の事実とはいえ、それでも広告は必要とされている。その効果をもう一度取り戻すには、インタースティシャル広告に関する認識を思い切って変えるべきである。すなわち、マーケター諸氏は、番組と番組の間に生じる時間枠のどれを選ぶかではなく、この古い手法をがらりと変えてみることを検討してみてはいかがだろう。
いまこそ、テレビにおける空いた時間帯ではなく、消費者の日常生活における「利用可能な部分」に焦点を当てるべき時である。すなわち、消費者が自分に関係のある製品やサービスに関するメッセージを受け取れる場所、タイミング、方法を探ってみるのだ。もはや追求すべきはインタースティシャル広告ではない。「ビビスティシャル広告」(vivistitial:日常生活のすき間)という新しいコンセプトである。
キャプティベイトのエレベーター広告
以下に、読者のみなさんがすでに経験していると思われるビビスティシャル広告の例を紹介しよう。たとえば、キャプティベイト・ネットワークが好例だろう。
ガネット・カンパニーの一部門であるキャプティベイトは1997年に設立された企業で、都市圏で働くプロフェッショナル層をターゲットに、実は『USAトゥデイ』とCNBC(ダウジョーンズとNBCが共同設立したニュース専門チャンネル)を合わせた以上の広告視認効果を実現している。